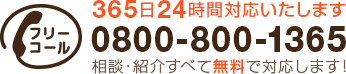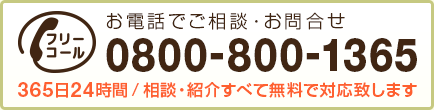訪問看護における労災請求ガイド!適用事例・手続き・必要書類まとめ
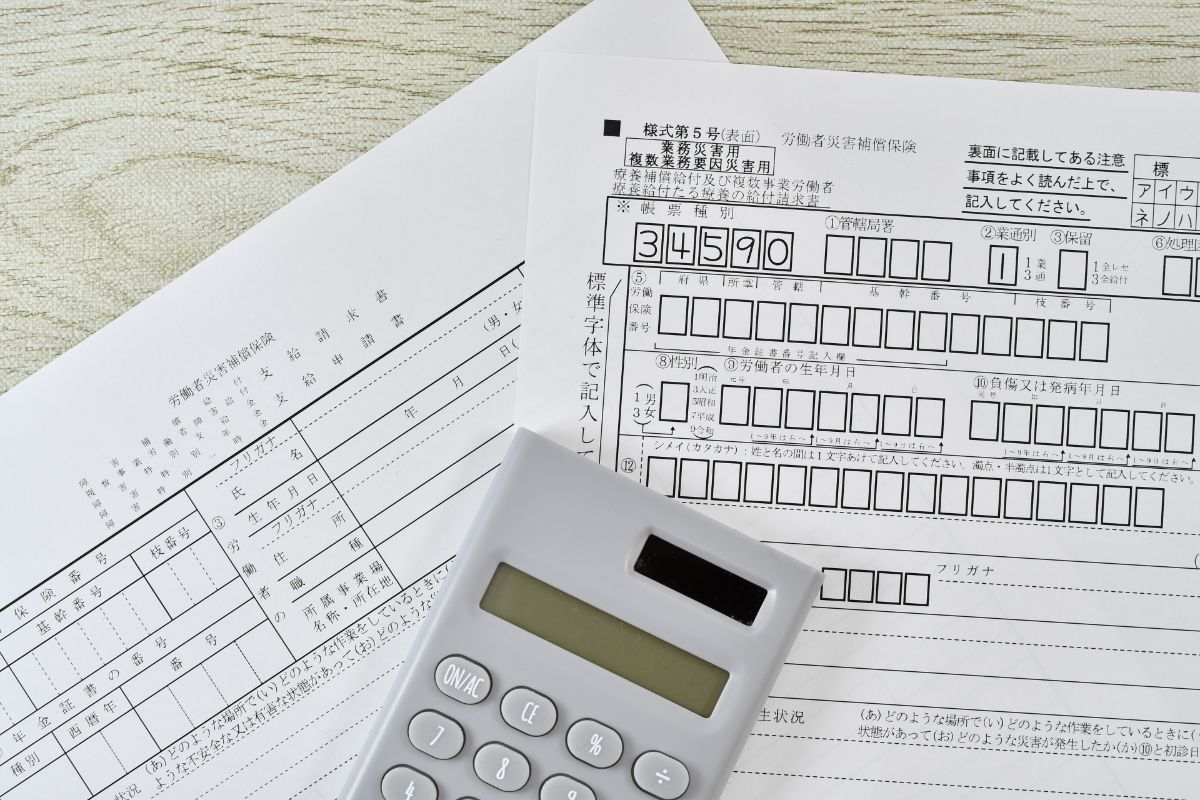
訪問看護で労災請求をしようとした際、「どの書類を準備すればいいのか分からない」「様式7号とレセプトの関係があやふや」と感じていませんか?さらに、様式ごとの記載例が見つからず、何度も労働基準監督署に足を運ぶ羽目になったという声も少なくありません。
現在、訪問看護に関連する労災請求では、様式5号から8号までの提出が必要となるケースが一般的です。特に様式7号にレセプトを添付する際、OCR様式での出力や、提出時の記載ミスなどが理由で申請が差し戻される例も報告されています。これらの失敗を避けるためには、様式の入手先や書き方を正しく理解することが不可欠です。
この記事では、申請に必要なすべての様式の内容と入手方法を網羅し、各様式の正しい記載ポイントや提出時の注意点まで、詳しく解説します。書類不備による支給遅延や再提出を防ぐためにも、正確な情報を把握しておきましょう。
最後までお読みいただければ、訪問看護における労災請求をスムーズに進めるための全知識が手に入ります。提出時の手間やトラブルを減らし、確実に療養補償給付を受け取るための手引きとして、今すぐ読み進めてください。
群馬県老人ホーム・介護施設紹介センターは、介護施設やサービスをお探しの方をサポートする情報サイトです。老人ホームや高齢者向け住宅の情報に加え、訪問看護や訪問介護など在宅で受けられる介護サービスもご案内しております。各サービスの特徴や利用方法、費用について分かりやすく説明し、ご利用者様やそのご家族が最適な選択ができるようお手伝いいたします。初めての介護施設選びや在宅介護の相談も安心してお任せください。

| 訪問看護・訪問介護も安心サポート – 群馬県老人ホーム・介護施設紹介センター | |
|---|---|
| 住所 | 〒371-0803群馬県前橋市天川原町2-41-8 NIWA-ALK2F |
| 電話 | 027-288-0204 |
訪問看護における労災保険の基本知識
労災保険の基礎知識と訪問看護への適用範囲
訪問看護の現場においても、業務中の事故や疾病は決して他人事ではありません。とりわけ、労災保険(労働者災害補償保険)は、訪問看護師が業務中に被災した際の重要な補償制度となります。労災保険は、労働者が仕事に起因して負傷、疾病、障害、または死亡した場合に、その療養費や休業補償などを国が支給する制度です。訪問看護師は、病院内の勤務とは異なり、屋外での移動や訪問先での作業など、労働災害のリスクが高い職種の一つです。労災保険の適用可否を正しく理解することが、事業所と職員の双方にとって極めて重要です。
労災保険が適用されるには、まずその人が「労働者」として労働契約に基づいて業務に従事していることが前提条件です。これは正社員だけでなく、契約社員やパートタイマー、アルバイトであっても該当する可能性があります。なお、個人事業主や業務委託の形式を取っている場合でも、実質的に指揮命令下にあると判断されれば、労働者性が認められるケースもあります。
訪問看護における労災適用の具体例としては、次のような業務中の事故が該当します。
- 自転車やバイクでの移動中の交通事故
- 利用者宅での転倒事故や器具によるケガ
- 感染症の感染リスクが高い場面での疾病発症
- 利用者による暴力やトラブルによる負傷
これらはいずれも、業務遂行中に発生した「業務起因性」と「業務遂行性」が認められれば、労災保険の対象となりえます。
また、労災保険は医療費や交通費だけでなく、「休業補償給付」や「障害補償給付」「遺族補償給付」などの幅広い支給制度を備えています。訪問看護師が業務中の事故で就業できなくなった場合、最大で賃金の80%相当が休業補償として支給されることもあります。
以下は、訪問看護における労災保険の適用パターンを整理した表です。
| 発生状況 | 労災保険の適用 | 解説内容 |
| 利用者宅での転倒事故 | 適用あり | 明確に業務中であり、場所も勤務場所として認定されやすい |
| 移動中の交通事故 | 原則適用あり | 訪問看護業務での移動が業務に含まれる場合、業務災害に該当 |
| 感染症の発症 | 条件により適用 | 業務上の感染と証明できれば支給対象。ただし証明の難易度は高い |
| 利用者からの暴力 | 原則適用あり | 精神的・肉体的被害ともに補償対象。被害報告書などが必要 |
| 通勤途中の事故 | 通勤災害として適用 | 出勤・退勤中の合理的経路上での事故であれば通勤災害に分類 |
これらの情報は、厚生労働省や労働基準監督署が発行する資料や労災保険法に基づいた制度解説に則った内容です。看護協会や労災関連の法律事務所による監修資料も併せて活用することで、より正確な判断と対応が可能となります。
訪問中・移動中の事故における業務災害・通勤災害の違いとは
訪問看護師が現場で遭遇する事故の多くは、業務災害または通勤災害に分類されます。両者はいずれも労災保険の支給対象となりますが、補償内容や証明責任の点で異なるため、違いを理解しておくことが非常に重要です。
業務災害とは、業務そのものが原因で発生した事故や疾病を指し、訪問先の利用者宅での転倒や移動中の事故などが該当します。通勤災害は、出勤や退勤時の通勤中に起きた事故のことを言い、私的な寄り道や遠回りをしていない場合に限り適用されます。
以下に、訪問看護における事故のタイプ別に、業務災害・通勤災害の違いを整理した表を示します。
| 事故の発生状況 | 該当災害区分 | 解説 |
| 訪問先で転倒し負傷 | 業務災害 | 業務中の明確な事故であり、補償対象として扱われる |
| 利用者から暴力を受けて負傷 | 業務災害 | 利用者との接触中であれば、業務起因性が高い |
| 訪問中に車で移動中に事故 | 業務災害 | 勤務指示に基づく移動中であり、業務遂行性が認められる場合が多い |
| 自宅から最初の訪問先へ移動中 | 通勤災害 | 通勤扱いとして保護されるが、寄り道などがあると適用外になることもある |
| 訪問後に別の場所で私用の買い物 | 不支給対象 | 私用の行為が絡む場合、業務性が否定される |
このように、労災申請においては「どこからが業務か」「どこまでが通勤か」という境界を明確に把握することが求められます。労災給付を正しく受けるためには、事故発生時の状況を客観的に記録し、第三者にも説明可能な証拠を残すことが極めて重要です。
労災保険対象者が訪問看護を利用する場合の制度併用ルール
医療保険・介護保険・労災保険の使い分けと優先順位
労災保険の対象となる人が訪問看護を利用する場合、注意すべき点は「どの保険制度が優先されるのか」という制度の優先順位と使い分けです。これは単なる保険の知識というより、請求ミスや給付漏れを防ぐための実務対応に直結する重要な内容です。
まず大前提として、労災保険は業務災害や通勤災害が原因で発生したケガや病気に対して補償するものであり、該当する限り最優先で適用されます。一方で、訪問看護の現場では、介護保険や医療保険といった複数の制度が併用される場面もあり、それぞれの制度の適用範囲を正確に把握しなければ、誤請求やトラブルに発展するリスクがあります。
以下は、保険制度ごとの特徴と優先順位を整理した比較表です。
| 保険制度 | 適用対象 | 優先順位 | 補足事項 |
| 労災保険 | 労働災害・通勤災害によるケガや疾病 | 最優先 | 労働基準監督署への申請と様式の整備が必要 |
| 医療保険 | 一般的な病気・ケガ | 2番目 | 業務上災害でないことを明確にしてから使用 |
| 介護保険 | 要介護認定を受けた高齢者の支援 | 状況依存 | 労災と重複しないサービスや要介護者の生活支援が対象 |
労災保険が最優先となる理由は、労働者災害補償保険法という法律に基づき、労働者に対する補償責任を国が直接負っているためです。たとえば、訪問中に転倒して骨折した場合、その原因が業務に起因するものであれば、労災保険が適用されます。その際、医療保険での請求やレセプト処理を先行してしまうと、二重請求として不正受給とみなされる可能性があるため、極めて注意が必要です。
また、訪問看護ステーションの事務職員は、利用者の保険適用状況を事前に把握し、どの制度でサービスを提供するかを確認した上で、記録や請求処理を行う必要があります。ここでの確認漏れが後々の返戻や支給拒否につながるため、制度理解は現場全体のリスクマネジメントにも直結します。
制度の使い分けを怠ると、次のような問題が発生する可能性があります。
- 請求区分の誤りによる返戻
- 利用者とのトラブル(費用の過剰請求や説明不足)
- 労災認定遅延による給付の遅れ
- 指導監査対象となるリスクの上昇
このような背景から、保険制度の併用に関しては、看護師、ケアマネージャー、事務職、そして管理者が共通理解を持ち、常に制度の最新情報にアクセスできる体制を構築することが必須です。
訪問看護における労災請求の流れ
労災請求に必要な様式の種類と入手先一覧
訪問看護における労災請求では、所定の書式を正しく整えることがすべてのスタートになります。現在、労災保険の手続きにおいては、厚生労働省や労働基準監督署が指定する様式(書類)を使用することが義務付けられており、OCR対応様式を使うことで処理の迅速化・正確性向上が図られています。
主に使用される書式は以下のとおりです。
| 様式名 | 用途説明 | 提出先 | 入手方法 |
| 様式5号 | 療養補償給付たる療養の費用請求用 | 労働基準監督署 | 厚生労働省HP、各労基署、都道府県労働局で取得可 |
| 様式6号 | 指定医療機関による療養費請求用 | 労働基準監督署 | OCR様式あり、PDFは厚労省サイトで配布 |
| 様式7号 | 訪問看護等の費用請求書(レセプト添付が必要) | 労働基準監督署 | OCR印刷推奨、書類セットで入手可能 |
| 様式8号 | 柔道整復師等が行う施術費請求書(主に柔整やあん摩) | 労働基準監督署 | オンラインPDFまたは直接窓口 |
これらの書類は、すべてPDF形式でダウンロード可能なほか、厚生労働省の公式ページから直接入手することができます。PDF版はOCR処理に対応しており、パソコン入力での記載も容易です。ただし、労基署提出時には「印刷時の指定サイズ(A4)」や「黒インクでの提出」など、細かなルールもあるため、事前に提出先に確認しておくことが望ましいです。
また、必要な書類は被災内容や申請の種類によって異なることもあります。たとえば訪問看護師が業務中に負傷した場合、本人の労災申請と同時に、看護ステーションからの療養費請求が必要になるケースがあります。その際は、以下の書類をセットで準備します。
- 様式5号:被災者本人による療養補償費用の申請
- 医師の診断書または訪問看護指示書(別紙様式)
- レセプト明細(様式7号に添付)
- 勤務状況証明書または就業証明(事業主発行)
さらに、看護ステーションが労災指定事業者でない場合、指定医療機関への登録が必要です。この際には「労災保険指定医療機関指定申請書」や「労災指定病院等登録(変更)報告書」などの別書式が必要となります。
様式5号・6号・7号・8号の記入例とポイント
労災請求書類を正確に作成するうえで、最もミスが多いのが「記入不備」や「記載内容の整合性不足」です。特に訪問看護においては、様式7号(訪問看護費用請求書)へのレセプト添付が必須であり、その正確性は審査に大きく影響します。
それぞれの様式の記入例と、記載上の注意点を以下に示します。
| 様式番号 | 書類名 | 記入ポイントと注意事項 |
| 様式5号 | 療養補償給付たる療養費請求書 | 被災者本人が記載。事故発生日、部位、通院日などを正確に記載。診療明細と一致させる必要あり |
| 様式6号 | 指定医療機関用療養費請求書 | 医療機関が作成。施設情報(事業所名、所在地、電話)を記載漏れしないこと。診療内容の概要も記載 |
| 様式7号 | 訪問看護費用請求書(レセプト添付) | レセプトと日付、内容を一致させる。単位数、請求金額の誤記が多く、OCR読取可能な字で記入 |
| 様式8号 | 柔道整復・施術等費用請求書 | 適応されるケースは少ないが、記載内容の整合性が強く求められる。施術内容を簡潔に記載する |
ここで特に重要なのが様式7号です。訪問看護ステーションが療養補償給付として労災保険から費用を請求する際、この様式にレセプト(診療報酬明細書)を添付しなければなりません。添付するレセプトは医療保険や介護保険で使用する様式とは異なり、OCR用に最適化されたレイアウトが求められます。
実務上の対策として、以下のような社内体制を整備することが推奨されます。
- 書類作成担当と訪問看護担当の情報共有の徹底
- 記載内容チェックリストの運用
- 提出前にダブルチェックを行う体制の構築
- 様式更新情報への定期的なアクセス(厚労省HP)
また、近年、全国の労働局や労基署で「電子申請」への移行が進んでおり、様式もOCR対応が強く推奨されています。PDFファイルをダウンロードし、PC上で編集・印刷することが可能な環境を整えておくと、申請処理のスピードと精度を向上させることができます。
まとめ
訪問看護における労災請求は、患者や事業者にとって非常に重要な制度でありながら、提出様式の複雑さや記入ミスによってスムーズな申請が妨げられるケースが多く見られます。特に様式5号から8号までの役割と記載方法を正しく理解していないと、支給遅延や再提出といったトラブルにつながりかねません。
現在、厚生労働省が提供する公式様式では、PDF形式とOCR対応の両方が用意されていますが、現場では手書きによる記載ミスやレセプト添付時の不備が依然として多発しています。労災保険の正確な適用のためには、業務災害と通勤災害の区分や、医療保険や介護保険との制度上の優先順位も理解しておく必要があります。
また、訪問看護ステーションの指定申請や、様式ごとの入手経路、提出先(労働基準監督署など)を把握しておくことも不可欠です。レセプト提出に際しては、対応する様式との組み合わせや記載内容の整合性が求められ、誤って提出すると事務手続きが煩雑化し、療養補償給付の支給に遅れが生じる可能性もあります。
「何をどう準備すればいいか分からない」「書類の書き方が曖昧で不安」と感じている方でも、正しい情報と正確な書類の記載によって、労災申請のハードルは確実に下げられます。特に申請件数が多い地域や、複数の保険制度が絡むケースでは、事前の情報収集と整理が失敗を防ぐ鍵となります。
正しい情報をもとに確実な申請を行い、支給までの期間短縮と申請トラブルの防止を実現していきましょう。制度を正しく理解し、申請作業を効率化することで、利用者や家族、そして医療スタッフ全体の負担を軽減できるのです。
群馬県老人ホーム・介護施設紹介センターは、介護施設やサービスをお探しの方をサポートする情報サイトです。老人ホームや高齢者向け住宅の情報に加え、訪問看護や訪問介護など在宅で受けられる介護サービスもご案内しております。各サービスの特徴や利用方法、費用について分かりやすく説明し、ご利用者様やそのご家族が最適な選択ができるようお手伝いいたします。初めての介護施設選びや在宅介護の相談も安心してお任せください。

| 訪問看護・訪問介護も安心サポート – 群馬県老人ホーム・介護施設紹介センター | |
|---|---|
| 住所 | 〒371-0803群馬県前橋市天川原町2-41-8 NIWA-ALK2F |
| 電話 | 027-288-0204 |
よくある質問
Q. 労災請求に必要な様式5号から8号はどこで入手できますか?OCR対応のものもありますか?
A. 労災請求に使用する様式5号から8号は、厚生労働省の公式サイトまたは労働基準監督署で入手可能です。近年はOCR様式での提出が推奨されており、PDF形式でもダウンロードできます。労働基準監督署ごとに対応状況が異なる場合もあるため、事前に確認すると安心です。提出書類の記載内容に不備があると再提出の対象となるため、取得先だけでなく記入方法にも注意が必要です。
Q. 訪問看護で労災請求を行う際、請求書とレセプトの添付方法はどうすればいいですか?
A. 様式7号を使用する際は、訪問看護のレセプトを必ず添付する必要があります。記載内容とレセプトの内容が一致しない場合は、支給決定に影響を及ぼすこともあります。OCR用紙に直接出力する場合や、クリップ添付で提出するケースなど、提出先の労働基準監督署が定めるルールに従ってください。提出にかかる手続きや支給までの期間は平均して約2〜4週間ですが、不備があるとさらに遅れるため注意が必要です。
Q. 様式6号の記入でよくあるミスと、支給が遅れる原因は何ですか?
A. 様式6号では、受診状況や治療開始日、療養内容などを正確に記載する必要があります。よくあるミスとしては、日付の記載漏れ、診療項目の記入不備、OCR形式での記入欄超過、レセプトとの記載内容の不一致などが挙げられます。これらのミスにより、労働基準監督署から訂正の連絡が入るケースも多く、結果的に療養補償給付の支給が数週間遅れることもあります。提出前には記載内容を複数人でチェックする体制を整えることが、支給の迅速化につながります。
会社概要
会社名・・・群馬県老人ホーム・介護施設紹介センター
所在地・・・〒371-0803 群馬県前橋市天川原町2-41-8 NIWA-ALK2F
電話番号・・・027-288-0204