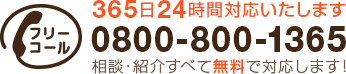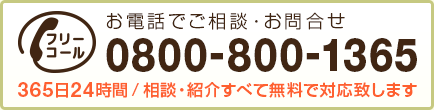訪問看護のご利用の流れを完全解説!申請からサービス開始までの安心手順

訪問看護を利用したいけれど、どこに相談すればよいか分からない、主治医やケアマネジャーとの連携はどうすればいいのか不安。そんな悩みを抱えていませんか?
在宅での療養を選ぶ方が増加するなか、訪問看護のニーズは年々高まっています。実際に、訪問看護の利用者数は年間で増加傾向にあり、医療保険や介護保険を活用したサービス提供が拡大しています。しかし、利用開始までの流れや申請方法、指示書の取得、契約・提供開始の手続きには多くの工程があるため、初めての方にはわかりづらいという声が多く寄せられています。
本記事では、訪問看護のご利用に向けた初期相談から、主治医による指示書の発行、ケアプラン作成、契約、そしてサービス開始に至るまでの全ステップを具体的かつ実践的に解説します。ケアマネジャーや看護師との連携のポイントや、厚生労働省の最新制度に基づいた注意点も網羅しています。
この記事を読み終える頃には、ご自身やご家族が訪問看護を安心してスタートするために「今なにを準備し、誰とどう関わればよいのか」が明確になります。読み進めることで、不要な費用や手続きの抜け漏れによる時間のロスを防げるはずです。自宅での療養生活をより良くする第一歩として、ぜひ最後までお付き合いください。
群馬県老人ホーム・介護施設紹介センターは、介護施設やサービスをお探しの方をサポートする情報サイトです。老人ホームや高齢者向け住宅の情報に加え、訪問看護や訪問介護など在宅で受けられる介護サービスもご案内しております。各サービスの特徴や利用方法、費用について分かりやすく説明し、ご利用者様やそのご家族が最適な選択ができるようお手伝いいたします。初めての介護施設選びや在宅介護の相談も安心してお任せください。

| 訪問看護・訪問介護も安心サポート – 群馬県老人ホーム・介護施設紹介センター | |
|---|---|
| 住所 | 〒371-0803群馬県前橋市天川原町2-41-8 NIWA-ALK2F |
| 電話 | 027-288-0204 |
訪問看護とは?ご利用前に知っておくべき基本知識とサービス全体像
訪問看護サービスの概要と対象者
訪問看護とは、在宅療養を希望する利用者の自宅へ看護師や保健師などの専門職が訪問し、医療的ケアや日常生活の支援、心身の状態管理などを提供する医療サービスです。高齢化が進む中、自宅での療養を望む人が増えており、訪問看護のニーズも高まっています。
対象者は、年齢や病気の種類に関わらず、医療的ケアを自宅で受ける必要があるすべての人です。たとえば、末期がん、脳梗塞後の後遺症、心不全、認知症、糖尿病による合併症などの病状を抱える方、人工呼吸器や胃ろうを使用している方も含まれます。また、精神疾患を抱える方、身体障害者手帳を持つ方、障害者総合支援法の対象となる方も含まれるため、身体的・精神的なサポートの両面から対応が求められます。
訪問看護の利用にあたっては、主治医の「訪問看護指示書」が必要です。これは医師が「この患者に訪問看護が必要である」と判断した上で交付する書類であり、医療保険または介護保険のどちらを使うかによって手続きが異なります。介護保険では、要介護認定を受けていることが前提です。医療保険を利用する場合は、難病、末期がん、精神科疾患など、厚生労働省が定める条件に該当する必要があります。
利用者は高齢者に限らず、在宅での療養が望ましいと判断されたすべての方が対象です。特に、障害者グループホームで生活している方や、生活保護受給者、単身高齢者など、社会的支援が必要なケースでは訪問看護が大きな役割を果たします。
地域によっては、訪問看護ステーションが提供できるサービスや訪問範囲が異なります。したがって、事業所の所在地や訪問時間帯、緊急時の対応体制などをあらかじめ確認しておくことが重要です。
提供される主なサービス内容と役割
訪問看護では、医療の専門知識をもつ看護師や理学療法士などが訪問し、多岐にわたるサービスを提供します。医師の指示に基づく処置だけでなく、生活面の支援やご家族へのサポートも含まれます。
提供される主なサービスには以下のような内容があります。
表:訪問看護で提供される主なサービス一覧
| サービス分類 | 具体的な内容 |
| 医療処置 | 点滴、注射、カテーテル管理、褥瘡(床ずれ)処置、人工呼吸器管理、酸素療法、経管栄養、インスリン注射 など |
| 健康状態の管理 | バイタルサインのチェック(体温・血圧・脈拍・呼吸など)、病状観察、薬剤管理、服薬指導 |
| 生活支援 | 清拭、入浴介助、食事支援、排泄介助、移動・移乗介助 |
| リハビリテーション | 関節可動域訓練、筋力トレーニング、歩行訓練、言語療法(ST)、摂食嚥下訓練 など |
| 精神的ケア | 不安の傾聴、うつ病・認知症などのメンタルサポート、家族支援 |
| ターミナルケア | 終末期の苦痛緩和、看取り支援、ご家族への精神的支援 |
さらに、訪問看護ステーションによっては24時間対応の体制を整えており、緊急時には夜間や休日の対応も可能です。これにより、急変時の安心感が生まれ、在宅療養の継続をサポートします。
また、認知症や精神疾患などを抱える方には、心の状態を観察しながら適切な対応を行う必要があり、精神科訪問看護のスキルも求められます。
このように訪問看護の役割は、単なる医療行為にとどまらず、利用者とその家族が住み慣れた地域で安心して生活を続けられるよう支援する重要な存在です。
訪問看護と訪問介護の違いとは?
訪問看護と訪問介護は名称が似ており混同されがちですが、提供するサービスの内容や担う職種、制度上の位置づけが異なります。
訪問看護は医療保険や介護保険の「医療系サービス」として、主に医療的なケアを行う看護師が対応します。一方、訪問介護は「介護系サービス」に分類され、ホームヘルパー(介護福祉士や初任者研修修了者など)が身体介助や生活援助を行います。
以下の比較表をご覧ください。
表:訪問看護と訪問介護の違い
| 項目 | 訪問看護 | 訪問介護 |
| 担当者 | 看護師、保健師、助産師、リハビリ専門職 | 介護福祉士、ホームヘルパー |
| 主な内容 | 医療処置、バイタルチェック、服薬管理、リハビリ、病状観察 | 排泄・入浴・食事の介助、掃除・洗濯・買い物などの生活援助 |
| 対象者 | 医療的ケアを必要とする方 | 介護が必要な方(要介護認定あり) |
| 利用保険 | 医療保険または介護保険 | 介護保険のみ |
| 医師の指示 | 必要(訪問看護指示書) | 不要 |
訪問看護は医師の指示書に基づき、疾患や症状に応じた専門的なケアを行うため、病状の悪化予防や再発防止に大きく貢献します。特に医療依存度の高い方や終末期の方には欠かせないサービスです。
一方、訪問介護は日常生活を自力で営むことが困難な高齢者や障害者の生活支援を目的としており、医療行為は行いません。ただし、両者は連携して利用することも多く、必要に応じて併用することでより充実した在宅ケアが可能となります。
訪問看護のご利用の流れ!申請から契約・サービス開始まで
利用に向けての初期相談・必要な準備
訪問看護を利用する際、最初のステップは「初期相談」です。この段階での情報整理が、後の手続きや連携のスムーズさに大きく影響します。まず相談先として挙げられるのが、地域包括支援センター、主治医、そしてケアマネジャーです。これらの専門職は、利用者や家族が抱える疑問や不安に対して的確にアドバイスを提供し、制度の利用条件や流れを案内します。
地域包括支援センターは、高齢者の総合相談窓口として全国の自治体に設置されており、要介護認定の申請や介護サービス利用の入口として重要な役割を担っています。まだ要介護認定を受けていない場合は、ここから申請手続きを始めることが一般的です。また、障害者の方は、自治体の障害福祉課や相談支援事業所などが相談窓口となります。
次に、主治医やかかりつけ医の存在が不可欠です。訪問看護の利用には、主治医の指示書が必要であり、これは法的にも義務づけられています。そのため、日頃から医師と良好な関係を築いておくことが、訪問看護導入の準備として非常に重要です。医師との面談時には、病状の変化、服薬状況、希望するサービス内容などを整理しておくと、指示書の発行がスムーズになります。
そして、ケアマネジャーの役割も非常に大きいです。介護保険のサービスを利用する場合は、ケアマネジャーがケアプランの作成を担い、訪問看護ステーションとの連絡調整を進めてくれます。訪問看護の対象となる疾患や状態は多岐にわたり、医療保険が適用されるケース、介護保険が適用されるケース、また障害者総合支援法に基づくケースなどがあり、その選定にも専門的知識が必要です。
以下のような情報を事前に整理しておくと、初回相談の質が高まり、以降の対応が効率化します。
相談時に準備すべき情報一覧(例)
| 情報項目 | 内容の詳細例 |
| 利用者の氏名・年齢 | 保険証・障害者手帳などで確認できるもの |
| 主治医の氏名と連絡先 | かかりつけ医、または病院情報 |
| 現在の病状や診断名 | 医師からの説明内容、検査結果など |
| 薬の服用状況 | お薬手帳、処方箋情報 |
| 日常生活の様子 | 食事・排泄・移動・睡眠状況など |
| 家族や介護者の情報 | 誰が主に支援しているか、緊急連絡先 |
| 希望する訪問日時や曜日 | 生活リズムや通院日などに合わせた希望 |
これらの情報は、相談時に口頭で伝えるだけでなく、簡単なメモにまとめておくことで、支援者側もより適切なアドバイスを行いやすくなります。特に初めて訪問看護を利用する方にとっては、不安や戸惑いも多いため、準備の段階から丁寧なサポートが求められます。
また、近年では、厚生労働省のガイドラインや訪問看護ステーションによる案内パンフレットが整備されており、それらを活用することで制度全体の理解が深まります。地域の訪問看護ステーションに直接問い合わせて資料をもらうのも有効です。
事前相談の段階で「どの制度を使うのが適切か」「費用はどのくらいかかるのか」「どんなサービスが受けられるのか」といった疑問を明確にしておくことで、以降の手続きも安心して進められます。訪問看護の導入は、医療的な支援を在宅で継続するための大きなステップであり、制度の適切な理解と準備が求められます。特に複数の制度(医療保険・介護保険・障害福祉)にまたがるケースでは、関係機関との情報共有と連携が極めて重要となります。
主治医からの訪問看護指示書取得と制度申請
訪問看護を正式に利用するためには、主治医から「訪問看護指示書」を発行してもらうことが不可欠です。この指示書は、訪問看護ステーションが医療保険・介護保険のもとでサービスを提供する根拠となるもので、法的に義務付けられている重要な書類です。具体的には、厚生労働省が定める訪問看護療養費制度に基づき、医師の管理下で適切なサービスを提供するために必要とされています。
まず、訪問看護指示書の発行プロセスを理解しておくことが重要です。以下はその一般的な流れです。
訪問看護指示書の取得手順(医療保険の場合)
- 利用者または家族が主治医に訪問看護利用の希望を伝える
- 主治医が診察を行い、訪問看護の必要性を医学的に判断
- 必要な場合は、診療情報提供書や検査結果をもとに内容を精査
- 「訪問看護指示書」を作成し、利用者側またはステーションへ交付
この流れは原則として医療保険を使用する場合のモデルですが、介護保険利用時でも指示書は必要です(特定事業所加算や医療ニーズへの対応時に特に重要)。また、障害者総合支援法に基づく訪問看護の場合も、医師の指示書が必要になるケースが多く、制度によりフォーマットや有効期間が若干異なります。
医療保険による訪問看護が適用されるケースの例
| 疾患または状態 | 内容の一例 | 適用制度 |
| がん末期 | 疼痛コントロールや終末期ケア | 医療保険 |
| 難病指定疾患 | ALS、パーキンソン病など | 医療保険 |
| 精神疾患 | 統合失調症やうつ病の在宅療養支援 | 医療保険・障害福祉 |
| 小児慢性疾患 | 医療的ケア児など | 医療保険 |
| 退院後の継続支援 | 点滴や褥瘡処置が必要なケース | 医療保険・介護保険併用 |
このように、疾患や利用者の年齢、要介護認定の有無などによって制度の適用が変わります。制度の選定と手続きには主治医の判断が欠かせず、またケアマネジャーや訪問看護ステーションとの綿密な連携が必要です。
訪問看護指示書には、以下のような情報が記載されます。
訪問看護指示書の主な記載項目
| 項目 | 内容 |
| 利用者情報 | 氏名・性別・年齢・住所 |
| 病名・診断名 | 主治医が診断した内容 |
| 目的 | 病状の管理、終末期ケアなど |
| 内容 | バイタルチェック、点滴、処置内容など |
| 回数 | 週何回・1回あたりの所要時間など |
| 有効期間 | 通常は14日間または1か月単位 |
なお、医療保険での訪問看護は、原則として「週3回」までの利用が標準とされています。ただし、重症者や終末期の利用者など、一定の要件を満たす場合は「週4回以上」の利用も可能です。そのため、訪問回数に関する調整も主治医との相談が必要です。
また、申請にあたっては、指示書の発行だけでなく、保険者(市区町村や健康保険組合)への提出や、ステーションとの契約、ケアプランへの反映が必要となります。訪問看護ステーションが代行してくれる場合もありますが、原則として情報の提供や同意が求められるため、家族や利用者自身の理解が重要です。
法的根拠においては、医療保険法、介護保険法、そして障害者総合支援法に基づいた枠組みの中で訪問看護が提供されており、制度の選択により報酬や利用条件、費用の負担割合も異なります。これらは厚生労働省が定める報酬告示やQ&Aなどを基に運用されており、最新情報を訪問看護ステーションや主治医、ケアマネジャーから提供してもらうことが望ましいです。
制度申請に必要な書類一覧(例)
| 書類名 | 提出先 | 備考 |
| 訪問看護指示書 | ステーションまたは保険者 | 主治医発行 |
| 診療情報提供書 | 必要に応じて | 医師が必要と判断した場合 |
| 介護保険証または医療保険証 | 保険者・事業者 | 制度確認に使用 |
| サービス利用同意書 | ステーション | 契約時に締結 |
| ケアプラン | ケアマネジャー | 介護保険利用時に必要 |
このように、指示書の取得と制度申請は訪問看護利用の根幹をなすステップです。正確な知識と段取り、そして関係機関との調整力が求められます。
訪問看護ステーションの選び方ガイド!失敗しないためのチェックポイント
サービスの対応範囲と対応時間の確認方法
訪問看護を受ける際、まず確認すべき基本要件が「対応範囲」と「対応時間」です。どれほど高品質なサービスを提供していても、利用者の住居エリアがサービス対象外であったり、必要な時間帯に訪問が受けられない場合には意味をなしません。特に在宅療養者や夜間の医療的ケアが必要なケースでは、24時間体制かどうかが極めて重要な判断基準になります。
例えば、以下のような項目を事前にチェックリストとして整理することが推奨されます。
サービス対応範囲と時間に関する確認項目
| チェック項目 | 確認すべきポイント例 |
| 対象エリア | 自宅住所が訪問可能エリアに含まれているか |
| 対応時間帯 | 平日日中のみか、夜間・早朝・土日祝日の対応があるか |
| 緊急時対応体制 | 急変時のオンコール体制、看護師直通連絡手段の有無 |
| 夜間対応の有無 | 深夜や早朝の訪問が可能か、看護師の人数や当番制の確認 |
| 訪問回数の柔軟性 | 週何回の訪問が可能か、回数の増減に柔軟に対応できるか |
| 医師との連携体制 | 主治医との連絡体制や報告手段が明確に構築されているか |
これらの情報は、事業所のパンフレットや公式ホームページ、または初回相談の際に確認することができます。特に「オンコール体制」については曖昧な説明をされることもあるため、「緊急時に誰に電話がつながるのか」「どれくらいの時間で訪問が可能か」といった具体的な質問を行うことが大切です。
また、ステーションによっては「24時間対応可」としていても、実際には委託先の看護師が対応するケースや、事前の契約が必要なケースも存在します。したがって、「実際に24時間対応する看護師は所属か外部か」「契約外の緊急対応は料金が発生するか」といった、細かい確認を怠らないことが重要です。
さらに、訪問看護ステーションが属する法人母体が大規模な医療法人や社会福祉法人であるかどうかによっても、対応力に差が出ることがあります。規模が大きいほどスタッフの配置に余裕があり、緊急対応力やバックアップ体制も整っている傾向にあるため、その点も参考にしましょう。
訪問可能エリアの境界線や曜日ごとの対応可否については、Googleマップ等で地理的に距離を確認することも一案です。特に、山間部や交通アクセスが不便な地域では、ステーションの対応範囲から外れている可能性があるため、細かい地理条件も加味する必要があります。
最終的には「その訪問看護ステーションが、自身や家族の生活スタイルと医療ニーズにどれだけ柔軟に対応してくれるか」が、選定の決め手となります。単に価格や立地だけでなく、時間・緊急・地理の3要素を中心に比較・検討することが、失敗しない訪問看護選びの第一歩です。
承知しました。それでは続きを以下に記載いたします。
評判・口コミ・実績の確認方法(レビュー・SNS・地域掲示板)
訪問看護ステーションを選ぶ際、実際の利用者やその家族からの「生の声」は、非常に有力な判断材料となります。制度や料金体系の比較だけでは見えにくい「対応の丁寧さ」「スタッフの雰囲気」「トラブルへの対処力」などを把握するには、公式情報だけでは不十分です。客観的な第三者の意見や評判を収集する手段を整理しておきましょう。
確認すべき主なポイント
- 同一人物の複数投稿や極端な評価がないか(公平性の確認)
- ネガティブな意見への事業所側の返信内容や対応姿勢
- 「看護師の対応」「緊急時の行動」「連携体制」などに言及した具体的な評価
- 更新頻度の高いSNSなどから事業所の透明性と信頼性
- 地域包括支援センターが他の利用者へ推奨しているかどうか
特に「低評価のレビュー」に注目することが重要です。低評価そのものではなく、苦情に対してどのような姿勢で改善や謝罪がされているかを見ることで、事業所の誠実さが浮き彫りになります。
また、Googleマップのクチコミは、同一地域に複数ステーションがある場合の比較に便利です。キーワード(例:丁寧、連携不足、夜間対応など)でフィルタしながら評価を読み取ると、ステーションごとの強み・弱みを見極めやすくなります。
さらに、地域のケアマネジャーや主治医、薬剤師などに直接ヒアリングできる関係があれば、紹介実績や連携状況、トラブルの有無などの“内部評価”を聞くことも有効です。行政窓口や支援センター経由での問い合わせであれば、公平中立な視点からの紹介が期待できます。
このように、公的情報と実利用者の声をバランス良く取り入れることで、訪問看護ステーションの選定精度は大きく高まります。情報を収集する際は「最新であるか」「信頼できる発信者か」を常に意識するようにしましょう。
まとめ
訪問看護をご利用になるまでの流れは、主治医やケアマネジャー、訪問看護ステーションとの密接な連携によって支えられています。特に初期相談からサービス開始までの間には、指示書の取得、制度の適用確認、ケアプランの作成、契約手続きなど、見落とせない重要な工程が多数存在します。
訪問看護の利用者数はここ数年で顕著に増加しており、医療保険と介護保険の両制度を活用するケースも一般的になってきました。その一方で、制度や料金体系の複雑さに戸惑う声も多く聞かれます。実際、「自分が対象になるのか分からない」「訪問看護と訪問介護の違いが曖昧」など、不安や疑問を抱えたまま相談に踏み出せない方も少なくありません。
本記事では、制度ごとの費用負担の違いから、精神科や障害者への対応、看護師の専門性の見極め方、さらには新規依頼時のチェックリストまで網羅的に解説しました。記事を読み進めることで、「どこに何を相談すべきか」「どの段階で何を準備すればよいか」が明確になったのではないでしょうか。
在宅療養を選ぶうえで、訪問看護は心強い支援のひとつです。時間をかけて正しい手順と情報を得ることが、結果的に無駄な費用や手戻りを防ぎ、ご家族の安心にもつながります。制度や流れを正しく理解し、信頼できる訪問看護ステーションと連携することで、安心して在宅での生活をスタートできるはずです。
群馬県老人ホーム・介護施設紹介センターは、介護施設やサービスをお探しの方をサポートする情報サイトです。老人ホームや高齢者向け住宅の情報に加え、訪問看護や訪問介護など在宅で受けられる介護サービスもご案内しております。各サービスの特徴や利用方法、費用について分かりやすく説明し、ご利用者様やそのご家族が最適な選択ができるようお手伝いいたします。初めての介護施設選びや在宅介護の相談も安心してお任せください。

| 訪問看護・訪問介護も安心サポート – 群馬県老人ホーム・介護施設紹介センター | |
|---|---|
| 住所 | 〒371-0803群馬県前橋市天川原町2-41-8 NIWA-ALK2F |
| 電話 | 027-288-0204 |
よくある質問
Q. 訪問看護の料金は医療保険と介護保険でどれくらい違いますか
A. 医療保険を利用する場合、訪問1回あたりの自己負担額はおおよそ800円から1,200円前後となり、1割負担であれば月額上限も高額療養費制度によって設定されています。一方、介護保険では1回あたりの基本報酬は20分未満で約312円、60分以上90分で約8,340円前後とされていますが、利用回数や加算条件により変動します。制度の適用や回数設定に応じて、ご利用者の費用負担は大きく変わるため、訪問看護ステーションと詳細に調整することが重要です。
Q. 訪問看護のご利用の流れで一番時間がかかるのはどこですか
A. 訪問看護の流れにおいて最も時間を要するのは「主治医からの訪問看護指示書の取得」と「制度申請に関わる手続き」です。特に医療保険でのご利用を検討している場合、主治医との面談調整や診断書発行、さらに指示書の発行までに数日から1週間程度を要することがあります。また、介護保険の場合はケアプラン作成やサービス担当者会議の開催も必要であり、全体で1週間から10日程度見ておくと安心です。
Q. 訪問看護で点滴や褥瘡管理をお願いすると追加料金は発生しますか
A. はい、医療的ケアである点滴や褥瘡管理は基本報酬に加えて処置内容ごとの加算が発生します。例えば、静脈点滴は1回あたり約750円から1,000円程度の加算、褥瘡の管理は処置内容や訪問頻度に応じて月間で2,000円〜4,000円程度の費用になるケースがあります。これらは訪問回数や保険適用範囲、さらに緊急対応が含まれるかどうかによっても変動するため、訪問看護ステーションでの事前確認が必要です。
Q. 精神疾患や障害を持っていても訪問看護は利用できますか
A. はい、精神科訪問看護や障害者総合支援法に基づく訪問看護の対象となる方は多く、医師の指示書があれば精神科訪問看護指示書や障害者医療証を活用して制度の支援が受けられます。精神疾患をお持ちの方には、専門の精神科看護師が対応し、服薬管理や生活支援、家族サポートも含めて提供されることが一般的です。また、自立支援医療制度を併用することで1割負担に軽減されるケースも多く、家計的な不安も軽減されます。
会社概要
会社名・・・群馬県老人ホーム・介護施設紹介センター
所在地・・・〒371-0803 群馬県前橋市天川原町2-41-8 NIWA-ALK2F
電話番号・・・027-288-0204